「ユング派」ではなく「分析心理学」として
「ユング派」という言葉を耳にすることが増えました。けれど、ユング自身が名づけたのは「分析心理学(Analytical Psychology)」でした。このコラムでは、その言葉の意味をあらためて見つめ直し、ユングの思想に立ちかえって「分析心理学」として歩むことの意義を考えます。
.
1.「ユング派」という言葉への違和感
最近、「ユング派」という言葉を目にする機会が増えています。創元社から刊行されたマリー=ルイーズ・フォン・フランツ著『ユング派精神分析の四本柱』(原題:Four Pillars of Jungian Psychoanalysis)も、その代表的な一例でしょう。
もちろん、翻訳上の理由によるものと理解はしています。英語圏では “Jungian Psychoanalysis” という語が広く用いられ、精神分析の大きな潮流の中にユング派を位置づける文脈もあります。しかし、ユング自身が自らの理論を指して名づけたのは 「分析心理学(Analytical Psychology)」 でした。
そのため、「ユング派精神分析」という呼称には、ユングの独自性がやや曖昧にされてしまうような違和感を覚えるのです。
.
2.「派」ではなく、「心理学」としてのユング
ユングは、フロイトとの決別以降、自らの立場を単なる精神分析の一分派としてではなく、「こころの全体性」を探究するひとつの心理学的体系として築き上げました。
それは、無意識を“理解すべき対象”としてだけでなく、人間存在の根源的な次元として“尊重し、ともに生きるもの”として見ようとする姿勢です。こうした立場を表すのに、やはり「分析心理学」という呼称こそふさわしいと感じます。
.
3.「ユング派」という言葉の変遷
日本では、AJAJ(日本ユング派分析家協会)などの活動や、国際資格としての「ユング派分析家」という呼称が一般的になり、「ユング派」という言葉が広く定着してきました。
わたくし自身もいつの間にか、流れに沿って違和感なく「ユング派」という言葉を使っていました。このホームページ上のコラムでも過去記事では”ユング派”という言葉を幾度となく用いています。しかし、改めてユングの言葉に立ち返ると、「ユング派=Jungian Psychoanalysis」という構図の中で、ユングの思想が“精神分析の枠”に収まりきらない広がりを持っていたことを忘れてはならないと感じるのです。
.
4. 初心にかえって ― 言葉を選ぶということ
ユングが生涯をかけて築いたのは、「分析心理学」という独自の世界観でした。それは、こころを分析し、理解することを通して、より深く生きる道を示す「心理学」です。
その本質を大切にするために、これからわたくしの文章の中では、「ユング派」という語ではなく、「分析心理学」あるいは「ユング心理学に基づく」という表現を用いていきたいと思います。
それは単なる言葉の選択ではなく、ユングが見つめた「こころの全体性」への敬意を込めた、ひとつの姿勢でもあります。
.
参考文献
- Marie-Louise von Franz, Four Pillars of Jungian Psychoanalysis(Spring Publications, 2004)
- マリー=ルイーズ・フォン・フランツ(松村由利子訳)『ユング派精神分析の四本柱』(創元社, 2020)
※この書籍の内容自体は大変勉強になるものです。
.
つくば心理相談室では、ユングの「分析心理学」を基盤とし、こころの深層をともに見つめる対話を大切にしています。自らの内なる声に耳を傾けたいとき、どうぞお気軽にお越しください。
.
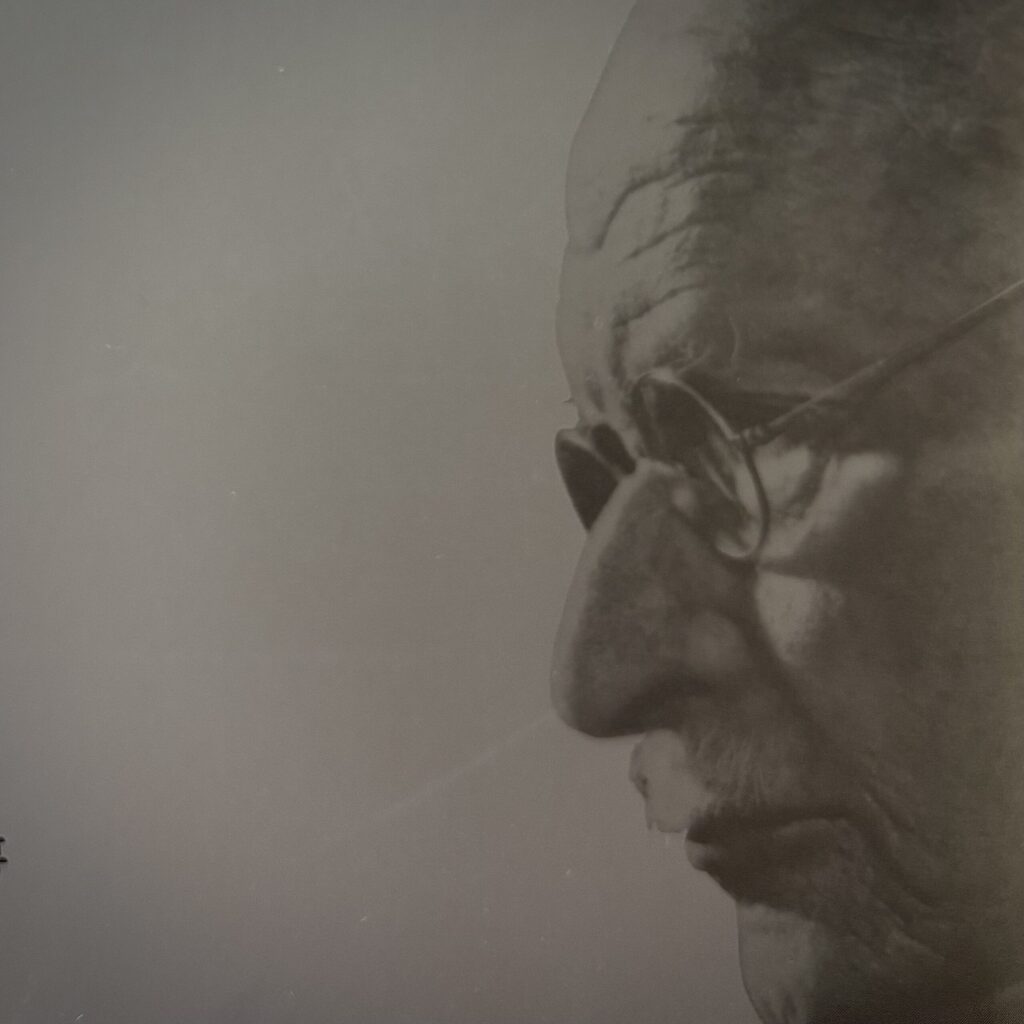
.

