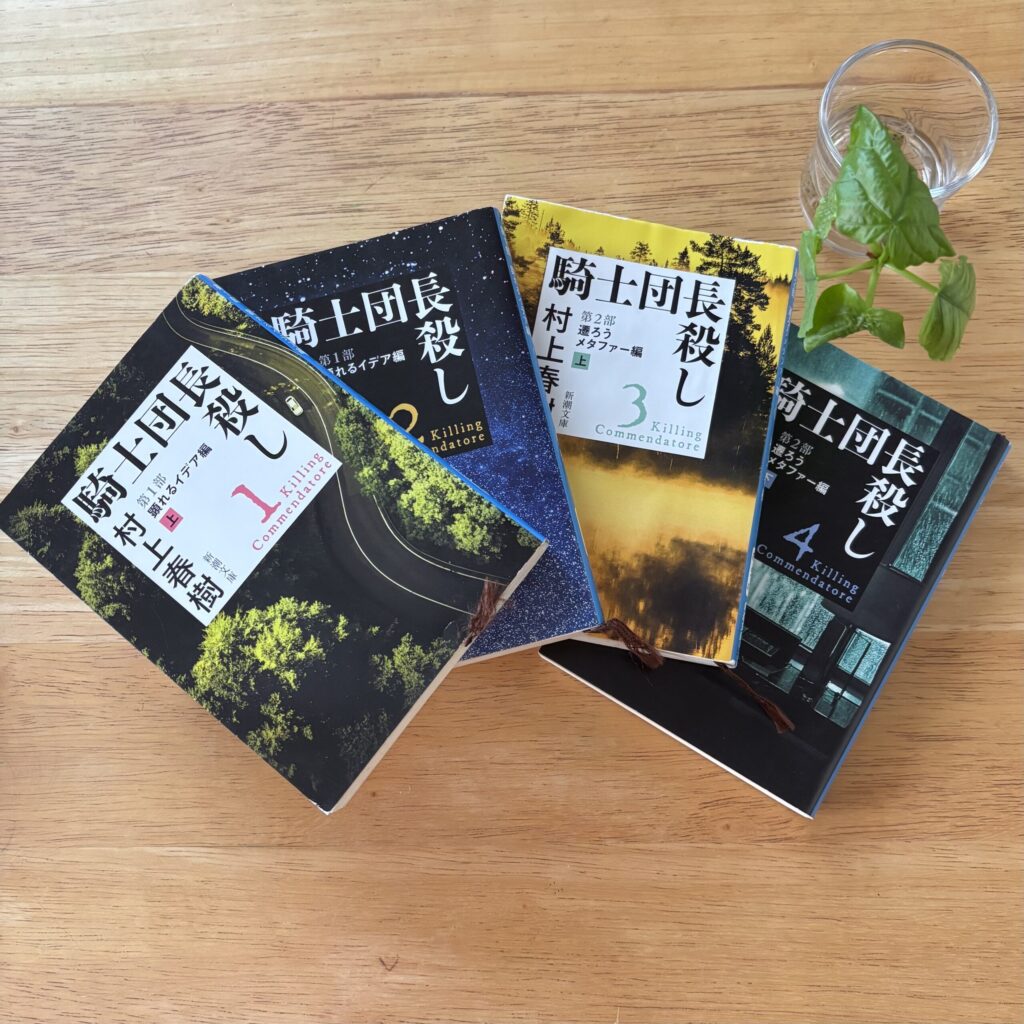村上春樹をユング心理学で読む ~『騎士団長殺し』にみる「無意識の物語」~
ずっと避けてきた作家、村上春樹。
けれど、ユング心理学の学びを深めるうちに、彼の作品の中に「無意識の象徴」が息づいていることを感じ、とうとう手に取った『騎士団長殺し』。
読んでみるとそこには、まるで夢のように日常と非日常が交錯し、こころの深層への旅が描かれていました。
本稿では、ユング心理学の視点から、この物語を少しずつ読み解いてみたいと思います。
.
1.なぜ今ごろ、初めて春樹?
ずっと避けてきた作家がいました。
その名は ― 村上春樹。
理由はいくつかあります。
「なんだかおしゃれすぎる? 世界観に飲み込まれそう」
「謎が多そうで、読んでもその世界観についていけなかったら恥ずかしいかも」
.
……つまり、完全に先入観です。
.
けれど不思議なことに、ユング心理学の世界では、彼の名前をよく耳にするのです。
心理学者が彼の小説を語り、講座や本で取り上げる。
まるで無意識から
「そろそろ読んでみたら?」
と呼びかけられているようでした。
そして、とうとう手に取った ― 『騎士団長殺し』。
.
これが予想以上に「夢」みたいな世界で。
日常と非日常の境界がゆらぎ、奇妙な出来事や象徴的な人物がポン、と現れる。
まさにユング心理学でいう無意識からのメッセージそのもの。
物語の中で出会う不思議な象徴を心理学の角度から読み解くと、本はただの物語から、自分の内面を映す鏡に変わっていくようでした。
そんなわけで 思いつくことを 少し書いてみようと思います。
.
2.「石室の穴」―無意識への扉
『騎士団長殺し』には、ひっそりと口を開ける「石室の穴」が登場します。
ただの地面の穴ではなく、物語の重心を揺らす不思議な存在。
河合隼雄は、洞窟や井戸、地下への道を「無意識への下降」の象徴として語っています。
日常という“地上”から離れ、意識の光が届かない深層へ降りていく―
そこは怖さと同時に、新しい自分と出会う可能性を秘めた場所。
石室の穴は、現実世界と異界の境目を曖昧にし、
主人公を“こちら側”から“あちら側”へと導く役割を果たします。
ユング心理学で言えば、この穴は自己(Self)への入り口といえるでしょう。
ただし、自己への道は一直線のエスカレーターではありません。
暗闇に足を踏み入れ、何が待っているかわからない不安と向き合いながら進む旅です。
主人公はこの狭い穴を這いつくばり、土にまみれ、全身に擦り傷を負いながら進みます。
その先で出会うのが ― “騎士団長”という象徴存在。
騎士団長は、単なる不思議キャラではなく、無意識の奥から送られた案内人。
つまりこの穴は、元型との出会いの通路でもあるのです。
わたくし達の日常にも、見えない「石室の穴」がふと現れることがあります。
それは新しい環境かもしれないし、予期せぬ出来事かもしれません。
怖いけれど、その先にはきっと自分を変える何かが待っている。
そんな気がして、進まないわけにはいかない ― そう感じる時があるのです。
.
3.騎士団長は老賢人?それともトリックスター?
『騎士団長殺し』に登場する小さな存在「騎士団長」。
彼は“人間”ではなく、“イデア”として現れます。
プラトン哲学のイデアとは、目に見える現実の背後にある「本質の型」。
ユング心理学でいう元型(アーキタイプ)に近い概念です。
つまり、騎士団長は主人公の内なる深層から立ち上がってきた象徴的存在。
では、彼はどんな元型にあたるのでしょうか。
ひとつには、知恵を授け、道を示す老賢人(Wise Old Man)。
主人公を導き、時に厳しく試す姿はこの元型と重なります。
けれど同時に、予測不能でユーモラスな言動を見せるトリックスター的側面も。
真面目さと滑稽さを行き来し、主人公の固定観念を揺さぶり続けます。
興味深いのは、主人公がこの騎士団長を「剣で刺す」という行為。
それは案内人を失うことではなく、その力を自分自身に統合するための象徴的な“死”と言えます。
河合隼雄の言葉を借りれば物語の「死」は、変容の始まり。
騎士団長を超えることで、主人公は自分自身の物語を歩みはじめるのです。
わたくし達の日常にも、そんな騎士団長のような存在が現れることがあります。
助言してくれる師や本、時には不思議な出来事など。
その存在を「刺す」勇気 ― つまり、自分の中に取り込んで歩き出すことが、変化の一歩になるのかもしれません。
.
4.終わりがもたらす始まり ― 象徴としての「死」
主人公は、騎士団長を「殺す」という決断を迫られます。
まさにこの本のタイトルです。
それは単なる物語上の出来事ではなく、自らの内なる世界において
「ひとつのものの死」を引き受ける体験でもあります。
ユング心理学において「死」はしばしば象徴的な出来事として語られます。
それは、自己の中で何かが終わり、古いあり方が崩れ、新しい可能性が芽生える契機。
河合隼雄はこう述べています。
「物語の中で人が死ぬことは、しばしば主人公自身の変容のために必要なものだ。」
主人公が騎士団長を刺し貫く場面は、まさにその瞬間です。
イデア=元型的存在である騎士団長を殺すことによって、主人公は自分の外にあった「超越的な象徴」を引き受け、血と土にまみれた人間の現実へと取り込んでいきます。
死を経て初めて、自己は変容するのです。
それは苦しみを伴い、痛みを避けることはできません。
けれども、その暗い過程をくぐり抜けたとき、人は以前とは違う仕方で
「生きている自分」を受け取ることができるのです。
騎士団長殺し ― この一見残酷な出来事は、だからこそ再生の物語なのです。
個性化の道を歩むわたくしたち一人ひとりにとっても、「小さな死」と「小さな変容」は日々の中で起こり続けています。
古い自分を手放すたびに、まだ見ぬ自分へと踏み出していく。
死は終わりではなく、変容の入口。
そしてその入口は、わたくし達それぞれの「物語」の中に、ひっそりと、しかし確かに開かれているのです。
.
終わりに
初めての村上春樹作品を、ユング心理学の視点からあれこれ述べてみました。
改めて、心理学とは、物語を通して自分を見つめる旅だと思うのです。
この旅が、あなたにとっても少しでもこころの響きをもたらすものであれば幸いです。
(敬称略)
.